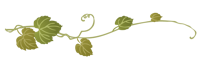
No.7 2015年5月発行
榎本好宏 選
| 「航」のこの号の着くころは、桜の花も散って、既に葉桜の候かも知れない。その桜の私の好きな言葉に、「花二十日」というのがある。「蕾七日、咲いて七日、散って七日」のことを言う。満開の桜は誰もが喜ぶが、蕾七日は待つ心を言い、散って七日は余韻の心を指し、いかにも日本人らしい美的感覚を示し得ていよう。 桜が散っても残花という言葉があり、少々見てくれはよくなくとも、桜蘂降る、なる季語が生まれ、葉桜で終わりと思いきや、桜の実まで余韻が続く。こんなことを思うと、つくづく日本人に生まれてよかったと思う。 ──今月の「航路抄」には、こんな一句を選んだ。 | 麦青む野火止といふ小学校 |
| 相川マサ子 | |
| 東京の池袋から西武線で行ける臨済宗の寺、平林寺の住所は、埼玉県新座市野火止となっている。ここには歴史があって、かつての川越城主が、川越街道沿いに入植地を作り、野火止用水を造り、玉川上水から水を引き、飲料水や灌漑用水に利用した、と記録にはある。その名が地名となり学校名として残ったのだろう。 野焼きや野火は、風の強い日に行おうものなら、火は一面に広がり人家にも類焼した。この野火を止めるための空濠があちこちに掘られ、更に後には消防団が立ち会うようになった。そんな野焼きの焦げ跡を残しながら、麦は青々と丈を伸ばしているというのだ。 | ◎ | 紙漉女美濃に生れたるばつかりに |
| 後藤 千鐵 | |
| 岐阜の美濃は、古くは奈良時代からの和紙の産地でもある。私の子供の頃、書道の練習には、もっぱら新聞紙や襖紙の裁ち落としを使ったが、展覧会に出す時だけ、普通の半紙より少し大判で、半透明の美濃紙が使えた。 それはともかく、紙漉きの仕事は真冬に行われるから大変辛い作業でもある。その辛さをじっと眺めていた作者は、思わず「美濃に生れたるばつかりに」と、呟いてしまったのだろう。 | ◎ | 一燈の漉きあがる紙嵩をなし |
| 花村 美紀 | |
| 前句同様これも紙漉きの一句。近場では、埼玉の小川も紙漉きで知られる。材を融かした水漕の中を、枠を搖らしながら簀(と呼んでいいのかどうか)の上に均等に紙の材がのると、その簀を、積み上げた漉き紙の上に重ね、簀をゆっくりはがしていく。この作業を重ねるうちに紙の嵩は徐々に増えていく。吊ってある一燈と、紙漉き人と、作者に、長い時間が流れていく。 | ◎ | つくばひの形に搖らぐ春氷 |
| 龍野 和子 | |
| 「つくばひ」は蹲踞と書き、茶室の入り口に備えられてある手水鉢のこと。その「つくばひ」に氷が張っていたが、春の訪れとともに融け、薄氷が浮くようになった。ただそれだけのことだが、「つくばひの形に搖らぐ」の形で手離し、読者に鑑賞の余裕を残しておいてくれたところが、手柄なのかも知れない。更に山口誓子の「せりせりと薄氷杖のなすままに」に、どこか通うところがある。 | ◎ | 雪吊りの縄の飾りも東振り |
| 宮下 徹 | |
| 毎年テレビのニュースでも報じられる金沢の兼六園の雪吊りに比べれば、東日本のそれは、作者の言う通り、まさに「東振り」に見えるのだろう。私の通い慣れた奥会津は、雪が多いこともあって、雪吊りも、ひたすら頑丈に作られている。森澄雄の句に、「もののふの東にをりて西鶴忌」があるが、この句の「東」にやや近い思いだろうか。 | ◎ | 春満月川幅少し広がりし |
| 酒井 洋子 | |
| 作者は福島県の奥会津、只見町の方。となればこの葉書きを投函するころは、雪がまだ深いはずである。「川」といえば、当然のことながら只見川だろう。昼間見ているときにはさほど感じなかったが、春の満月の中で見ると、心なしか川幅が少し広がって見える。そこに酒井さんの詩が生まれた。 | ◎ | 海明けや漁師の家に春燈 |
| 坂本 洋子 | |
| 一句の前書きに「オホーツク」とある。となれば、岸辺までぎっしり詰まっていた流氷が退き、海が明けた日となる。いよいよ漁の季節になるが、かつてなら春告げ魚の別名を持つ鰊漁だが、今ならどんな魚を獲るのだろう。その海明けと共に、漁師の家々には早朝から燈がともり、出漁の準備が始まった、というのだ。 | ◎ | 船のやうぼうたんの島漂へる |
| 日高俊平太 | |
| 牡丹を島内一面に咲かせる島があるのだろう。その景が海上から見え、さながら島そのものが漂っているように見える、いや漂っているのだ。そうでないと詩にはならない。 | ◎ | お降りや彩あらたまる太鼓橋 |
| 髙部せつ子 | |
| 寺などの池や川に架かる太鼓橋は、大方が朱塗りである。この日は初詣でだがあいにくの雨、いやお降りである。そのせいか、見慣れた橋も、雨によって色も変わり、少々改まった気分になった、というのだ。 | ◎ | 鳥帰る杉一幹の高さかな |
| 中村いはほ | |
| 北に帰る鳥を見上げた作者、その目の高さに杉一幹がそそり立っている。御神木であろうか。帰る鳥が、杉の高さを改めて教えてくれたようでもある。 | |

