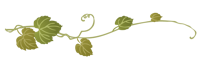
No.23 2018年1月発行
榎本好宏 選
| のっけから難しいことを言うようだが、日本語は大和言葉と漢語と外来語の三つで成り立っているという。大和言葉というと、一般には『万葉集』や『源氏物語』などに使われているような難しい言葉と思われがちだが、広義の大和言葉とは私達が日常友人と話している言葉くらいに思ってもらえればいい。また、漢語の方も、一見漢詩の一部の言葉と思いがちだがそうではなく、音読みの漢字を組み合わせただけの言葉なのである。例えば音読みの「青」(せい)と、同じく音読みの「天」(てん)を組み合わせると「青天」と漢語的になるが、これを「青」を「あお」と読み、「空」(そら)の訓読みと組み合わせて「青空」とすれば、これは一種の大和言葉になる。 現代俳句を一般的に見ると、音読みの文字を組み合わせた漢語的な読み方の言葉があまりに多過ぎ、表現が固くなる。その一因は終戦直後の昭和二十一年に生まれた「当用漢字」(一八五〇字)にある。後に文字数を少しふやした「常用漢字」もできたが、これらの欠点は、漢字の音読みは多く残したが、訓読みがめったやたらに減らされたことである。このことについては、いずれかの機会に詳しく書くが、この欄では、俳句に大和言葉を多用することをぜひ勧めたい。 今月の巻頭句は、福島県の奥会津にお住まいの馬場忠子さんの次の句を選んだ。 | この村のすべての息が雪となる |
| 馬場 忠子 | |
| 奥会津には馬場姓が多いので、ここでは忠子さんと呼ぶ。忠子さんは、私がこの原稿を書いている数日前、念願の句集『忠子俳句集成』を「航出版」から出したばかりである。その句集の序文は私が書いたが、その作品の多くが奥会津という風土を重く負って作られている。どんな俳句名人がこの地に入って作っても、忠子さんの作品は越えられないであろうと、私はそう思っている。 今号の巻頭句も、そんな風土を強く負った一句である。「この村のすべての息」と、決して難しい言い方はしていないが、その言葉の奥に言い知れぬ深い風土がある。 この忠子さんの住む町(かつては村)は、奥会津でも雪の深い所で、四、五か月は雪に埋もれるところである。だから雪囲いはできているだろうか、雪除けの準備は整っているだろうか、野菜などの食糧の確保はできているだろうか、病人が出たらどう手筈を取るのだろうか――私が考えただけでも、たくさんの雪への備えが思われる。この句の言う「村のすべての息」とは、それらすべてを言っているのである。そして、雪は約束どおり既にやってきたのだ。 | ◎ | 島々の形に灯り神の旅 |
| 田中 勝 | |
| 陰暦の十月、全国の神々は出雲大社に集まり、翌年の縁結びについて合議する。このための道中がここで言う「神の旅」である。作者の田中さんは、その旅を夜と見定め、海上に見渡せる八百八島を神の眼下に置いてみた。日が落ちて間もない頃でもあったのだろう。見下ろせる島のどれも家の灯がともり、生活が営まれている様子が神の目にも映じる。出雲で諮(はか)られる縁結びのきっかけも、こんな灯の中にいくつか散見できるのかも知れない。そんなことどもをも想像させてくれる一句である。 | ◎ | 鰯雲仁右衛門島へ手漕ぎ舟 |
| 後藤 千鐵 | |
| 「仁右衛門島」とは、千葉県南部の鴨川市の海岸近くにある小島のことだが、この島は代々平野仁右衛門を名告る個人所有の島である。とは言え、源頼朝や日蓮上人の遺跡まである。陸から数十メートルしか離れていないのに連絡船に乗らねばならないが、作者は手漕ぎ舟で渡った。そこが良かったのだろう。私も、この近くに実家のある鈴木真砂女さんの紹介で出掛けたが、船を下りると、すぐ目の前の海べりに岡本眸さんの大きな句碑があるだけでなく、島中が句碑だらけでもあった。ただ後藤さんの「手漕ぎ舟」の一語は、頼朝や日蓮ゆかりの眺望のいい、かつての小島に私達を引き戻してくれるはからいがある。 | ◎ | 買ひ足して無花果父の忌なりけり |
| 赤木 和子 | |
| 私の疎開していた群馬では、どこの農家も井戸端の近くに、この無花果が植えてあり、秋になると赤紫色の実を付ける。私達子供は通りすがりにこれを捥いで皮ごと食べるが、食べ過ぎると舌が荒れて難儀したものである。 作者のお父さんもこの無花果が大好きだったので、毎年の忌日には仏前に供えることにしているのだろう。今年の忌日に、その無花果が少ないのをめざとく気付いた身内が、「少なすぎるわよ」とでも言ったのだろう、急遽買い足しに走った、ということなのだろう。 | ◎ | 障子貼るのみの帰郷となりにけり |
| 太田かほり | |
| 聞くところによると太田さんは、四国に住む高齢のお母さんの介護のため、教職の余暇をみては時々帰郷していたという。この一句もそのことを詠んだものだが、私が関心を持つのは「障子貼るのみの帰郷」の表記かも知れない。人様に「母の介護のため帰郷するのよ」と言うのとは違って、帰郷する自らの心の重さを「障子貼るのみの帰郷」と、その原因の軽さに置きかえようとする、一種の自己誘導の心の計らいの一句と私には見える。そのお母さんも昨年二月に他界された。太田さんの心中いかばかりかと思うのである。 | ◎ | 賜りし急がぬ時間実むらさき |
| 宮下とおる | |
| 現代の社会は、普通の勤めや生活をしていても絶えず時間に追いかけられながら生きていかなければならないように仕組まれている。そんな中、ふっと湧くように現れた「急がぬ時間」。それを作者は「賜りし」と謙虚な言葉で受け止める。その微妙な心のありようと、それに合わせた季語「実むらさき」との間に、微妙でほのぼのとした、言いがたい感性が立ち昇る。 | ◎ | 待宵の外湯へ廊下軋ませて |
| 花村 美紀 | |
| 十五夜の前日の十四日の月を「待宵」とか、「小望月」と呼ぶ。温泉宿に泊まっている作者は、この月を外湯で見たく、長い廊下を急ぐが、その床の軋む音にさえ、早く見たい思いがつのる。 | ◎ | 雀らの枯葉のごとく寄り合へり |
| 砂田久美子 | |
| 稲を刈ったあとの落穂などが田の面にある間、雀は群れて田の周りを飛んでいるが、餌もなくなると民家の周囲にやって来る。そんな雀が、ちょうどその頃散り始める木々の落葉のように見えるというのだ。 | ◎ | 箒目に紅葉ゆるして仁王門 |
| 佐藤 享子 | |
| 仁王の像を左右に安置した門をくぐると、箒目がきれいに見える寺の庭に出るが、その上に既に楓などの落葉が散り始めているという景だろう。「紅葉ゆるして」の言葉が優しい。 | ◎ | 説法跡走りの林檎供へあり |
| 石井 公子 | |
| 鎌倉市内に日蓮の辻説法跡があるように、各地には高僧の説法跡が残っている。「林檎」とあるから信州か、東北辺りのそれであろう。「走り林檎」の言葉が土地の人との深いかかわりを思わせる。 | |

