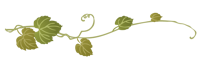
No.16 2016年11月発行
榎本好宏 選
| いつもの月なら、巻頭にふさわしい数句を目の前に置き、思案している、私にとって一番充実している時間なのだが、今月はそれがない。最前から、上位で選んだ俳句を何度も読み直しているのだが、心を打つ句が見つからない。 私の所属していた「杉」のことだが、創刊して間もないころ、主宰の森澄雄も私と同様に悩んだのだろう、理由も書かずに、巻頭を据えるスペースに芭蕉の一句だけを置いた。その芭蕉の句も五十年前のことだから忘れたが、会員の誰もが緊張した。いま、そんなことを思い出している。 そんな中、次の一句を巻頭に選ぶことにした。 | 炎天を支ふ青田となりにけり |
| 安部由美子 | |
| 同じ「青田」といっても、いろいろあることは、私も群馬の農村地帯に疎開し、子供ながら田作業を手伝わされたから、よく知っている積もりでいる。稲の生長は早く、何度か田の草取りをしているうちに、農家の専門用語でもある分蘖(株張り)が進み、このころから青田と呼べる風景になる。 やがて梅雨に入ると茂みはしっかりとし、田水も外から見えなくなり、梅雨が明けるころは、少しオーバーだが、中国の伝説にもあるように、稲の葉の上に人間が横たわれるようになる。「炎天を支ふ青田」はそんな季節を指しているが、この眼差しの裏には、田を植えたころから、ずっと見渡してきた長い時間がひそんでいることを感知すべきだろう。 | ◎ | 相続の口火を切りぬ夕蜩 |
| 天野 祐子 | |
| ある年齢になると相続のことが気になるものである。自分または自分達夫婦の死を仮定することだから、実子と言えども、話を切り出すには勇気がいる。ましてや、中には、土地の人から一目置かれる家柄のお宅などでは大変なことだろう。加えて遺産相続もあって、時には子供同士の争いにもなるから、一層厄介なことである。 このお宅でも、その相続の話を、さりげなく夕食の席に招いて切り出したのだろう。すると、はかったように蜩が鳴き始めたのだ。私の想像では、すべてが穏便にはかどったと思う。そんな思いも蜩が支えてくれているのかも知れない。 | ◎ | 誰がための糸瓜の水を取るのやら |
| 原山テイ子 | |
| よその家の庭に植えてある糸瓜を見ての一句だろう。正岡子規にも、辞世の句として 痰一斗糸瓜の水も間にあはず など、糸瓜の作品を三句残しているが、昔は痰切りや喉の薬として糸瓜水を使っていた。また、この糸瓜水は女性の化粧水としても使われている。「いる」と書いたが、私が福島の只見町を仲間と訪ねた折、「航」同人の飯塚恒夫さんの奥さんから、女性の仲間だけが、この糸瓜水をいただいたことがある。作者も、よその家の庭に見た糸瓜から、「一体だれが使うのだろう」と思ったに違いない。 | ◎ | 帽子ぬぎ茅の輪をくぐるもう一度 |
| 山口悠紀子 | |
| 俳句作りのために改めて書くまでもないが、茅の輪は、六月祓えの折、茅萱や藁で大きな輪を作り、鳥居などにかけ、これを三回くぐって身を祓い清める儀式。そのくぐり方も、洋数字の「8」の形に歩を進める。人波にまじって茅の輪をくぐったはいいが、帽子をかぶっていたので、二回目は慌てて帽子を脱いでくぐった。日本人のある年齢以上の人は、神仏や貴人の前では帽子をかぶってはいけないこととしているから、一周目はかなり慌てた様子が、この一句の裏に読んで取れる。 | ◎ | 一面は夫への一句流灯会 |
| 前田 智子 | |
| お盆の十五日、または十六日の夜、灯籠に火を灯し、川などに浮かべて流す行事が、流灯会とか灯籠流しと呼ぶ行事である。川の汚れなどからやめたところも多いが、作者の住む山梨県都留市辺りでは、今も行われているのだろう。亡き人への思いや絵を描く人もあるが、俳人でもある作者は、灯籠の一面に、亡きご主人への思いの一句を書いたというのだ。ご主人への思いの深さが読み取れる。 | ◎ | 木洩れ日の他は動かず蟻地獄 |
| 後藤 政子 | |
| 蟻地獄が多いところと言えば、寺の本堂の近くの乾いた土の辺りか、欄干の下の砂地に多くはある。こんな場所には蟻が沢山うろついていそうだが、まず見当たらない。その巣の辺りに木洩れ日が差し込んでいるが、風で木の葉が揺れるので、つれて木洩れ日も動く。それが「木洩れ日の他は動かず」なのだろう。微細な景をよくぞ見届けたものである。 | ◎ | 釣糸の絡まつてゐる大毛蓼 |
| 早野 和子 | |
| 正直、私もこの花を知らないが、歳時記で調べるとタデ科の一年草で、夏から秋にかけて、紫紅色の小花を集めて花序をつくる——とあるから想像のつく花である。「釣糸の絡まつてゐる」とあるから、川や沼の縁に咲いているのだろう。この「釣糸の……」の具象が、この一句の手柄になっている。 | ◎ | 盆踊り科の良い娘は嫁候補 |
| 渡部 華子 | |
| 普段街中で見かける折は、あまり気にもかけていなかったが、盆踊りの夜、浴衣姿で現れた娘さんの、所作等の科の佳さに改めて驚いたのだろう。「嫁候補」のまなざしは、当の男性でなく、親か祖父母のそれであろう。 | ◎ | 桐は実に余生ゆるゆるほどほどに |
| 末永 淳子 | |
| 私もいま余生の真っただ中にいて、この句の言うように、「ゆるゆるほどほどに」が目標だが、実際は、この見事な生き方に反する生活を送っている。それが大方だろう。そして、取り合わせとして置かれた季語の「桐は実に」が実に見事だ。
| ◎ | 生かされぬ折り鶴なほも原爆忌 |
| 山口 光子 | |
| 作者の年齢は四十三歳。投句の全五句が戦争にまつわるもの。投句用紙の通信欄にも「戦後七十一年目も、戦争について、戦争を知らない世代なりに考えてみました」とある。原爆忌のたびに折ってきた鶴が、どこか形式化してきていることへの反魂として、私には読める。 | |

