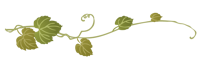
No.39 2020年9月発行
榎本好宏 選
| コロナ禍のため、半年近く家居の日々を余儀なくされてきた人々にとっては辛いことだったろうと思う。ふだんなら俳句仲間との会話や句会をしながら何とかしのいだり、「航」への投句で自らの思いの丈を発散できたのにそれができない。 その影響は「航」の雑詠欄の投句にも明らかに出始めてきた。まず投句用紙表の通信欄への書き込みが妙に増え始めていることである。ほとんどの方はここにコロナ禍による日常の辛さを書き、投句する作品も私から見ると変わりつつある。どう変わってきたかと言えば少々声高に自己を主張する方々が増えた。 もともと俳句とは、「いかに声高に言うこと」ではなく、自己を抑制しながら「いかに言わないか」を心掛ける文芸なのに、このところ逆の現象が出てきていることが残念である。 こんな私の思いを支えてくれる作品にも何句か出遭えた。この稿はそんな作品を取り上げてみたい。 | 太棹のやうに仕舞の男梅雨 |
| 永井 環 | |
| 昔から梅雨は農家にとって大事な雨だった。稲の育ち盛りだから絶えず水が必要で、それも満遍なく降ってくれなくては困る。となれば雨量の多い男梅雨のような降り方が、この梅雨に適っていた。昔からそうだが、この男梅雨現象は梅雨の末期にやってきて、今年の梅雨のごとく、九州、中国地方に降った大雨現象のように降る。この一句は、男梅雨の雨の降り方を「太棹のやう」と比喩の形でとらえている。 太棹とは、義太夫節などに使う棹の太い三味線であると同時に、義太夫節そのものを指して言う。これに比べて棹の細い三味線を細棹と呼ぶが、男梅雨の降り方と、時には雷鳴をとどろかせて降る雨の音は、まさに「太棹のやう」が適っている。 | ◎ | 四葩(よひら)咲く愛子の墓の向き斜め |
| 後藤 千鐵 | |
| 鎌倉にある五山の一つ、寿福寺の墓苑の景である。寿福寺に虚子の墓があることから虚子一門の墓があることでも知られる。この句の言う愛子こと、森田愛子の墓もその一つである。鎌倉は山地だから平らなしつらえの墓は作れず、崖の岩場をくりぬいて作った〝やぐら〟なる墓が多く、寿福寺もその一つである。虚子の墓もそんな〝やぐら〟仕立てで、一年中参拝者が訪れている。 その虚子の墓に向き合うと、右側の平地に一基妙な墓がある。他の墓は整然と同じ向きに建っているのに、この一基だけが虚子の墓の方を向いているのだ。これが虚子の女弟子、森田愛子の墓で、愛子の恋人が建てた。 虚子の墓から見て前方の右側には、娘の星野立子の墓もあるから、これらの空間に立つと、虚子と立子が愛子を見舞うために福井県を訪れた物語りまで景が発展するから不思議だ。寿福寺はまた四こと紫陽花の似合う寺でもある。 | ◎ | 田水引く隣に麦の熟れてあり |
| 栗原 満 | |
| 田に水が引かれ田植えの準備が始まるころと言えば、田と隣り合わせの麦畑ではちょうど麦の熟れ時を迎える。麦秋である。この作者の住む群馬県の近くに疎開していた私の経験では、当時の麦と言えば主食の大麦で、麦秋はやや黄ばんだ色に見えた。これに対して時々見られた小麦の麦秋は少し赤みがかって見えたから、子供達は小麦の穂を両掌でしごいた粒を噛んで、手製のチューインガムを作ったものである。 | ◎ | 振り回すことは出来ぬか青大将 |
| 齊藤 眞人 | |
| 前句の小麦の穂のチューインガム同様、私の少年時代の思い出につながるのがこの一句かも知れない。少年時代の私達の周囲にいたのは青大将とか縞蛇といった毒を持たない蛇が多かったので、少年の多くは勇気をふるって蛇の尻尾をつかんで振り回したり、地面に叩きつけて遊んだりもした。ただ少年達が警戒したのは毒蛇で、これらの頭は三角形をしていたから皆用心した。こうした一句の世界を知らない人も今の世には多い。 | ◎ | 杜若(かきつばた)謡を復習ひゐたりけり |
| 下山永見子 | |
| この一句の鑑賞のむずかしさは、季語「杜若」と、「謡」以下のフレーズの取り合わせにあるのかも知れない。この取り合わせに妙な知恵の解釈を加えては駄目で、両者を並べて見てその間に立ち昇るエーテル状のものに相づちが打てるかどうかだけで十分なのである。私はこの一句に大いに相づちが打てる。 | ◎ | 緞帳(どんちょう)のゆるりと上る夏芝居 |
| 真下 忠男 | |
| 夏芝居の多くは歌舞伎に使われていた言葉のように私には思える。歌舞伎界の夏は著名役者の多くが夏休みを取り、日ごろ舞台に上がらない若手の役者も出てくる。昔の話をすれば、東京だと歌舞伎座以外の、花道の短い東横ホールなどで舞台が持たれた。この句の夏芝居には、そんな気軽さも感じられようか。 | ◎ | 内風呂のあけすけの声西瓜切る |
| 花村 美紀 | |
| かつての風呂場は屋外に作られ外風呂と呼んでいた。これに対して屋内に作るものを内風呂といった。夏のこと風呂場は開け放っておくから子供の声も外に響く。そんな中、風呂を上がった順に切った西瓜にありつく、といった場面だろうか。 | ◎ | 後退(あとずさ)りらしき足跡植田中 |
| 早野 和子 | |
| かつての田は皆後退りで植えたから、田の中に足跡も残ったが、機械植えの今の田にはそんな痕跡は残らない。恐らく機械の入れない山の田か、補植のため人の入った跡だろうか。 | ◎ | さざなみの力集まる余り苗 |
| 上春 那美 | |
| 田を植えた後、苗が浮いて流れることを浮き苗といった。これを補植するために、田植えの後田の隅に余り苗を浸してあった。この余り苗にまで、田の面を吹く風が及んでいるのだ。 | ◎ | 星祭揃ひの兵児帯(へこ)を下ろしけり |
| 露木 敬子 | |
| 子供にとって新しい衣類を着させてもらう着下ろしは楽しみの一つだった。その着下ろしも祭りにちなんで行われることが多く、この句のように星祭りにちなんで行われた。 | |

