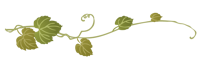
No.22 2017年11月発行
榎本好宏 選
| 現在「航」に転載している俳誌「俳壇」の連載「四季巡詠」だが、作品の締め切りが二か月前なので、かなり苦労している。例えば十月号の締め切りは八月十日なので、作品を作った時の季節と発表の時節が大分ずれてしまうことになる。 こんな時思い出したのが、飯田龍太さんの名言だった。ずいぶん昔のことになるが、龍太さんが当時、NHK学園の俳句通信講座の責任者をされていた。ある日突然、龍太さんから手紙が来て、そこの機関誌「俳句」に近世の作家論を書くように、との指示だった。 四年間の連載が終わると、龍太さんの山廬(当時の山梨県境川村=現在は笛吹市)に招かれ、奥様の手料理をご馳走になった。その折、龍太さんの言われた言葉が、「今現在の季で俳句を詠むより、一か月先の季を見渡して作った方がいい」だった。これは金言である。「俳壇」の連載も、龍太さんの言葉に従って、雑誌発行月に近い季語の句を作っている。何か新しい世界に足を踏み入れた思いが私にはある。 さて、今月の「航路抄」の巻頭句だが、こんな作品を選んだ。 | 虹二重虚子と愛子の墓の距離 |
| 後藤 千鐵 | |
| 高浜虚子の墓は鎌倉の寿福寺にあり、鎌倉特有の岩山をえぐった矢倉墓である。その墓から十数メートル左手に、弟子の森田愛子の墓はあり、整然と並んだ墓石の中に、愛子の墓だけが虚子の方向に向いて建っている。この墓を建立したのは夫の伊藤柏翠である。後藤さんの句は、その事を言っている。 戦雲急を告げる頃虚子は小諸に疎開し、そこから見えた浅間山にかかる虹から、 浅間かけて虹のたちたる君知るや 虹たちて忽ち君の在る如し 虹消えて忽ち君の無き如し の三句を作り、愛子に書き送っている。 虚子は〝愛子もの〟と呼ばれる小説を五編書いているが、その一つ『虹』が世に出た年の昭和二十二年四月一日に、二十九歳の短い一生を終えている。そのいまわの床から虚子宛てに、「ニジ キエテスデ ニナケレド アルゴ トシ アイコ」なる電報を打っている。 だいぶ省略はしたが、これが後藤さんの一句の後ろにある世界の一部である。 | ◎ | 我の手で早く打たせて蕎麦の花 |
| 鈴木 隆 | |
| 鈴木隆さんは福島県三島町に住み、奥会津に私が入るときは運転手役をつとめてくれ、私の泊まる宿へは自分で打った蕎麦を持参、これまた自分で茹でて出してくれる。今年亡くなった「航」の同人で、元三島町長の斎藤茂樹さんが現役のころは、町の総務課長を長く勤めた。 この隆さん、町きっての蕎麦打ちの名人だが、ここでは蕎麦を打つと言わず「蕎麦をぶつ」という。麵棒に巻いた練り蕎麦を伸し、板にこすりつけず、叩き付けて延ばすからこう呼ぶ。こんな名人にとって、蕎麦の花は心を一層急かせるものなのかも知れない。 | ◎ | 降る星のひとつ混じりぬ夜干梅 |
| 安部由美子 | |
| 漬けた梅は三日間日干しにし、残る三日を夜干しにして仕上げる。私の子供の頃はお菜がない時代だったから、弁当の多くは、ご飯の真ん中に梅干しを置いただけの「日の丸弁当」だった。梅干しはしゃぶった後、種を歯で割り、中にあるピーナツ状の天神様とも呼ばれるものまで食べた。しかし、親から「天神様を食べると頭が悪くなる」と言われ、食べない子もいた。少し話がそれたが、その夜干しの梅の中に、流れ星がまぎれこんだというところが、この一句の詩でもあろう。 | ◎ | シベリアを語らぬ亡夫や夏の星 |
| 平峯 秀子 | |
| 終戦一週間前に参戦したソ連軍は、戦勝と同時におよそ六十万余の日本人をシベリアに移送し、強制労働に従事させた。この方のご主人もその一人だったのだろうか。最近、航出版から出た日高俊平太さんの句集『霜琳』にも、 月待ちのラーゲリに遺書そらんじて の一句があるが、帰国する際、書き物などは持ち出させないので、友人の遺書をそらんじている―の意だが、ご主人は奥さんといえど、人にはとても言えない体験をしたのだろう。(「ラーゲリ」=強制収容所) | ◎ | とどろきもうねりとなるや立佞武多 |
| 浦田 吟竜 | |
| 佞武多と書いて、「ねぶた」と読めば青森市などの七夕の行事だが、立佞武多となると、こちらは「たちねぷた」と読む五所川原市の行事である。かつて成田千空さんの招待で見せてもらったが、高さ二十三メートルもある立佞武多が繰り出すさまは、まさに「とどろき」と「うねり」の言葉にふさわしい。 | ◎ | 煙立つ田圃の増えし豊の秋 |
| 中村いはほ | |
| 早稲、中稲、晩稲の順に田は刈られ、刈られた順に藁くずなどを刈田で燃やしていく。今は機械化で藁くずはあまり出ないが、でもこんな晩秋の光景はまだみられる。ただ、煙が鉄道などの障害になるので、行政が管理しているようだ。 | ◎ | 鮑取り磯鑿の柄に魔除け印 |
| 太田 直史 | |
| 水底の岩にはりついてる鮑(あわび)を搔きとる作業は、危険に違いない。そのため磯鑿(いそのみ)の柄に魔除けの、たぶん焼き印が押してあったのだ。磯にいる漁師達の側に何気なく置いてある鑿をのぞいて、そのことを知った作者は、さぞや驚いたことだろう。 | ◎ | 爪紅に風のひと押し爆ぜにけり |
| 佐藤 享子 | |
| 爪紅(つまぐれ)とは鳳仙花のこと。名付けのもとは、この花を爪紅(つまべに)に使ったからだとされる。秋になって熟した実は、ちょっと触れただけではじけて種を散らす。この句は、風のひと押しで爆ぜたというのだ。 | ◎ | 縁側に律の声して種瓢 |
| 天野 祐子 | |
| 正岡子規は、自らの病気に使うこともあった瓢を窓辺に植えていた。その瓢が「種を採れるほどになりましたよ」と妹の律が縁側から子規に声を掛けているのだろう。こんなふうに子規一家と作者を現在形で描くことも、俳句ではできる。 | ◎ | とんぼうや誰も素通り草の罠 |
| 金田 弥生 | |
| 私達の子供の頃も、丈の高い草を二つ束ねて結んで輪にしたものを草罠と言い、人がつまずいて倒れるのを楽しんだが、それと同じものだろうか。もう、草々も黄ばみ始めた風景が見えてくる。 | |

