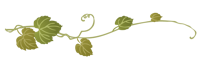
No.24 2018年3月発行
榎本好宏 選
| 私の若かった昭和三十年代のころの話だが、各新聞社は毎月一回、おのおのの社の信条や社是を紙面にのせていた。その中の一社の社是に、「新聞記者たる者、世の木鐸たれ」といった内容の一項を掲げている新聞社があった。大手新聞社の大方は明治時代の初期の創刊だったから、周囲には文字の読めない人や世相、常識を判断できない人の層も多かったので、社是に残るこんな一文の理解はできたが、およそ昭和三十年代には相応しくないと私は思っていた。その社是、それから間もなく紙面から姿を消した。 社是から「世の木鐸たれ」の一文は消えたが、世の人を覚醒させ、教え導く、という木鐸精神は新聞紙面のあらゆる文章にまだ残っていて、私などは絶えず不快感を持ち続けてきた。 当時あちこちに文章を書いていた私の文章論の第一は「文章を書く人と、それを読む人の目線は同じ高さでなくてはいけない」だったから抵抗が強かった。 同じことは俳句の文体にも言える気がする。仮に作者が「これでどうだ」だとか、「かくあるべきだ」風の作品を読者に示したとすれば読者はついていけない。文章と同じように、俳句も作者と読者の目線の高さは一緒でなくてはならない。この欄に相応しくない文章を書いたが、今月の巻頭には迷いなく次の一句を選んだ。 | 梳く藁の匂ひのたちぬ冬隣 |
| 露木 敬子 | |
| 機械化の進んだ今では、傾斜地や、よほどの小さな田でなければ、稲の手刈りの風景は見られない。この一句の作られた風景も、どの田でも稲の手刈りの行われていた時代のものかも知れない。 藁を梳くという作業は、刈って脱穀した稲藁に付いている葉の部分を取り除く作業で、かつては、稲の穂のところを握り、竹か鉄で出来た千歯扱き(せんばこき)を通して除いた。こうして仕上げた茎だけの藁は、お正月飾りに使ったり、縄を綯うなどに利用した。このほか千歯扱きにかけない藁は筵を編んだりなど、使い道はいろいろあった。 収穫の終わった稲藁は生活の必需品だったから、農家の家の辺りは、藁の香が満ち満ちていた。その様子は「匂ひのたちぬ冬隣」と書かれたが、うまく表現したものである。ただ、こんな光景が見られなくなった現在が少し寂しい。 | ◎ | ぼろ市の素見の客で通しけり |
| 後藤 千鐵 | |
| 私の知っているぼろ市は、東京の世田谷のものくらいしかないが、なぜ「ぼろ」なのか調べてみると、江戸市中で集めたぼろを野良着の補修用として売った(『ブリタニカ』)説から、わらじに編み込むぼろ切れを売った(『日本国語大辞典』)説まで、いろいろある。現代のぼろ市は、これらとは無縁だが、店先にはちょっと心の動きそうな品々が並んでいて楽しい。それを見るだけで買わない「素見」で通したところが面白い。そこに、遊里を見物するだけで遊ばないという素見の本義を重ねると、一層面白くなってくる。 | ◎ | 宿墨の乾涸びてゐる三日かな |
| 柏倉 清子 | |
| 古いことを言うようだが、一月二日に行う書き初めは、その年の恵方の方角に向かって座り、詩歌などを書いた。こんな本格的なものでないにしろ、今でも一月二日に家中が集まって書き初めをするお宅は多いだろう。にぎにぎしく行った書き初めだから、書いた文字の方に互いの関心が集まり、肝心の硯のことを忘れてしまう。翌三日、改めて硯をのぞいてみると、宿墨が干上がってからからになっている。誰にでも経験のあることであろう。 | ◎ | 芋の露丹沢籠めて零れけり |
| 太田 直史 | |
| 私の住む横浜辺りでも、晴れた日には美しい大山連山が望める。この句は、もっと大山寄りの土地に吟行に行った時のものだろうか。畑の芋の葉の露には、間近に見える丹沢のおのおのの山が写り揺れている。しかも芋の葉の上をころがりながら……。時に強い風が吹くと、丹沢を写している露が、芋の葉から転げ落ちるというのだ。この作者は落ちると言わずに、少々情を込めて「零れけり」と表現した。 | ◎ | 残し置く青菜一畝雪催ひ |
| 岡本りつ子 | |
| 岡本さんの住む福島県の奥会津は雪の多い所。そろそろ雪のころともなれば、大方の冬野菜は取り込んでしまうが、青野菜だけは取りたてを食べたいから一畝だけ残しておくというのだ。とはいうものの、間もなく本格的な雪の季節、どのくらい保(も)つのだろうか。 | ◎ | 記憶より小さき母校花八手 |
| 齊藤 眞人 | |
| こう言われてみると、誰もがなるほどと思う。子供のころの思い出といえば、校庭に多少の遊具のある学校が大方の子供達の遊び場だったことである。縁あって数十年後に訪ねてみると、思っていたより狭い。これは誰もが感じる思いである。その校庭に、記憶から取り残されていた花八手が咲いていたのだ。 | ◎ | 漆刷く雪は静かに降り積もり |
| 花村 美紀 | |
| かつて、私の属する「件の会」の集いの「さろん・ど・くだん」に、輪島在住の髹漆(きゅうしつ 物に漆を塗ること)作家で、国の重要無形文化財保持者(人間国宝)の小森邦衛さんをお招きしたことがある。漆塗りを見たことのない私だが、その講話を聴き、また実作のビデオと作品を見て感じたことは、花村さんの言う「雪は静かに降り積もり」の静謐さから生まれるものだろうと、今改めて思う。 | ◎ | 木遣うた手斧始の東照宮 |
| 栗原 満 | |
| 投句葉書のメモ欄に「世良田東照宮の御手斧始め式を見学」とある。世良田(せらた)とは群馬県の、私が戦時中に疎開した町の隣村で、おそらく日光東照宮の末社であろう立派な社だった。叔母の招きで私も子供のころ見た覚えがあるが、その祭りの厳格さだけは覚えている。嬉しいことに、この春入会した栗原さんは、私の卒業した太田高校の同窓生である。 | ◎ | 滾つ湯にごろんごろんと寒卵 |
| 早野 和子 | |
| 戦中戦後の食糧難の時代に育った世代にとって、寒卵は最高の馳走であった。その寒卵が茹だって鍋底をころがる音は、同世代を生きた早野さんにも、極楽から聞こえてくる音に感じられたに違いない。 | ◎ | 初鏡晩年の母をるやうな |
| 天野 祐子 | |
| 初鏡は女性にとって大事な一種の儀式でもあるだろう。数年前までは、その鏡の前に母と立って、髪をいじったり、着付けを直してあげたりしたのだろう。初鏡は、作者と母との懐かしい共同作業の場であったのだろう。 | |

