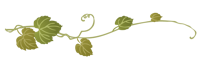
No.12 2016年3月発行
榎本好宏 選
| 今年の正月は、雪国の多くでも、雪のないまま明けた。この欄の締め切りも一月十日だから、投句葉書きの通信欄には、雪の降らなかった正月の喜びが綿々と綴られていた。特に会員の多い福島・会津の人達の喜びが多かった。ところが、航路集の選を始めた同十四日になると、この暖冬が一変して、全国での大雪。ふだん雪にまったく縁のない、私の住む横浜にも数センチの雪が積もった。寒さに弱くなった私も、この日は一歩も外に出られなかった。それはそれとして、地球が少しずつ狂い始めてきている。 さて、今月の巻頭句には、次の一句を選んだ。 | 雲の蛇笏水の龍太や花辛夷 |
| 青山 幸則 | |
| この作者は、私が二か月に一度通っている沼津の句会の会員である。去年の句会の折、「山廬(飯田蛇笏、龍太の住居)に行ってきました」ともらされたことがあったので、その時の作品かも知れない。それにしても、「雲の蛇笏水の龍太や」とは、まことに見事な把握だと思う。 去年の十一月号のこの欄で、次巻頭で採った佐藤享子さんの 湘子の沖草田男の沖葉月尽く の場合は、湘子と草田男に「沖」を詠んだあまりにも有名な句があるから、鑑賞する私はそれらの作品を下敷きに書けたが、この一句の読み方は、そうではあるまい。 もちろん、蛇笏には雲の、龍太には水の名吟は数多あるが、この作者は、雲や水にこだわりなく、両者の沢山の句を読み、その結果、大摑みでも「雲の蛇笏」と「水の龍太」の把握ができた。これこそが、「航」創刊に当たり掲げた「こころざし」に言う、「おのおのが持つ、無意識下のやわらかい自己の発現」に適っているように思えてならない。 | ◎ | 雪螢舞ふやいづかたよりとなく |
| 松崎 一男 | |
| 雪螢とは、綿虫とか大綿などとも呼ばれるアブラムシ科の虫である。私も若いころ、勤めの関係で三年余札幌にいたから知っているのだが、夕方、この虫が風花のように舞い始めると、その後、本物の雪が降り始める。札幌辺りでは、十一月の後半から十二月の初めの初冬に現れる。この作者の住む会津若松も雪国だから、こんな風に現れるのだろう。何気ない「いづかたよりとなく」の表現が、螢虫の在りようを見事言い当てている。 | ◎ | 野菜屑焚きて出小屋の秋収め |
| 太田 直史 | |
| 場所によって、自宅と耕作地が離れている場合は、畑に近い所に小屋を建て、耕作中はそこに住む。これが出小屋だろう。私のよく通う福島の会津では出作り小屋と呼んでいた。北海道の知床半島に点々と散在する鮭番屋もそんなものかも知れない。この句、秋の収穫も終え、小屋を閉めるに際して、野菜屑などを燃やしている光景だろう。私の編んだ『奥会津歳時記』にも、秋の季語として「出作り小屋閉づ」を入れた。 | ◎ | よき言葉閉ぢ込めて縫ふ菊枕 |
| 太田かほり | |
| 干した菊の花を入れて作る菊枕は、その匂いや風情とともに、頭痛や目の病いに薬効があるとされてきた。この作者は菊枕を縫いながらよき言葉を閉じ込めたという。一体どんな言葉だったのだろうか。「ホトトギス」の歳時記に〈寝返れば醒めれば匂ふ菊枕 土居牛欣〉なる句があるが、その折、詩の一節が聞こえるのかも知れない。 | ◎ | 閼伽桶のすこし重たき三日かな |
| 山口悠紀子 | |
| よりによって正月の三日が命日のご遺族がおられるのだろうか。正月のことだから、墓には人影がない。そんな中を作者は、水を満たした閼伽桶を提げて墓に向かうが、いつもと違って桶が少し重い。そう言えば、元日から二日間、お節だけを食べて、体を動かさなかったことに、ややしばらくして気付いたのだろう。 | ◎ | 塩鮭とササラ電車の便りかな |
| 宮下とおる | |
| 年末になると、北海道在住の知人から、毎年塩鮭を送ってくるのだろう。その荷の中に手紙が入っていて、今年も雪が多く、ササラ電車が出動しました、とでも書いてあったのだろう。今ではテレビでも放映されるから読者もご存知だろうが、市電の先頭に付けられた束子状のものを回転させ、線路上の雪をのけるのがササラ電車。作者にとって、塩鮭の到来とササラ電車出動ニュースは、まさに歳末の到来を意味することなのだ。 | ◎ | 赤蜻蛉待つといふにはあらねども |
| 各和 正雄 | |
| 九十五歳になられた各和さんは、奥さんともども養護施設に入られた。生活には便利だろうが、自宅とは違うから、そうは出歩けない。そんな中、本当は赤蜻蛉を見たいのだが、「待つといふにはあらねども」と言う。これは男独得の「照れ」なのである。 | ◎ | どの家も雪垣了へししじまかな |
| 馬場 忠子 | |
| 馬場さんは豪雪地帯の南会津町にお住まいの方。そのため雪に対する備えが大変だ。それまで、あちこちの家から釘を打つ音や木を切る音がしていたのに、今は雪垣の作業が終わったのだろう、辺りがピタッと静かになったというのだ。 | ◎ | 賽銭の如く投げ入れ大根買ふ |
| 渡辺 幸弓 | |
| よく農家の入り口や畑の隅に、野菜の無人スタンドが置かれてあるが、この一句もそんな場面なのだろう。新鮮な大根の代金を箱に入れると、さながら賽銭のような音がしたというのだ。 | ◎ | ためし掃きしてより帚木おほふりに |
| 安部由美子 | |
| 帚木は帚草とも言うように、昔から帚にしてきた。作者も葉の散った帚木を帚に仕立て、試しに掃いてみたら具合がいいので、大きく振って掃いたというのだ。 | |

