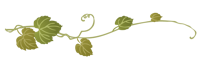
No.11 2016年1月発行
榎本好宏 選
| 明けましておめでとうございます。貴重な航路集の誌面をお借りして一言お祝いを申し上げます。この「航」も創刊三年目の年に入りました。創刊の「『航』のこころざし」に掲げた「おのおのが持つ、無意識下のやわらかい自己の発現」を目指し、今後も俳句に新しい境地を開いていく所存です。 その新年号には、次のやわらかな一句を、巻頭に選んだ。 | 瓜の馬父は歩いて来るだろう |
| 長田 敬子 | |
| 「瓜の馬」は、ここに改めて書くまでもないが、盂蘭盆会の折に、瓜に苧殻を刺して脚とし、馬に見立て盆棚に供える。一般には、胡瓜や茄子を使うことが多い。何故と孫にでも問われれば、「この馬に乗って、仏様が帰ってくるのよ」などと年寄りが答えることになっている。 この「瓜の馬」に対する作者の思いは少し違っていた。生前の故人は歩くことが好きで、滅多に車や自転車を使わなかった。だから「瓜の馬」など使うはずはないと思いながら、そのことを孫にも告げたかも知れない。些細なことで、そこにユーモアが生まれた。もう一点加えるとすれば、表現が平易である。芭蕉は、俳諧は「三尺の童にさせよ」、つまり子供にさせよと言ったが、この一句、まさに「三尺の童」の叙法でもある。 | ◎ | 行徳の月に漕ぎだす塩荷舟 |
| 花村 美紀 | |
| 「行徳」とは、千葉県市川市の、東京湾に面する土地の名。この地はかつて塩田として知られ、江戸では、「行徳」というと塩の代名詞だった。埋め立てられる前は、江戸川の河港として栄えていた。この一句、作者も知らない時代の風景だろうが、こんな風に現在形で描かれると、読者は、眼前の景が現在のものに思えてくる。そこが俳句の面白いところでもある。 ついでに書くが、江戸時代に行徳で生産されていた塩は四万石だったから、大人口を抱える江戸では足りるはずがない。そこでとられたのが、大阪湾から塩廻船で運ぶ策で、行徳産の二十倍に相当する八十万石の塩が送られてきた。 | ◎ | 夕月の傾きほどの片想ひ |
| 坂本 洋子 | |
| 「夕月」とあるから、夕方、西の空にある若い月と、逆に東の空に昇ってくる満月より少し若い月の両義に解釈できるが、一句の成り立ちから想像すると、夕空に見える月だろう。となると、若い頃のややロマンチックな片思いとも取れるが、あながちそれだけとは限るまい。相手は何も感じていそうもないのに、自分の心中では、ひそかに相手を恋い慕う。これは何も若者の特権ではなく、年齢にかかわりなく、心中に顕ってくるほのぼのとしたもの、誰にでもある。そんな思いを「夕月の傾きほどの片想ひ」と比喩の形で描かれると、「なるほど」と得心がいく。 | ◎ | 輪中いま稲架高々と廻らせて |
| 早野 和子 | |
| 改めて書くまでもないが、集落や農地を洪水などから守るために、周りに堤防を築いた地域が輪中。知られているものは、木曽、長良、揖尾の濃尾三川であろう。堤防で囲われているから農地も少なく、しかも収穫した稲を干す稲架も広く構えることが出来ず、ひたすら高く高く積み重ねていく。いかにも輪中らしい光景が描かれた一句だ。 | ◎ | 鰯雲消防ホース櫓より |
| 齊藤 眞人 | |
| 私が子供の頃を過ごした田舎の町には、集落ごとに火の見櫓があり、火事や米軍の空襲の折には半鐘が撞かれた。すると、消防小屋から手押しポンプが出動していった。消火して帰ってくると、消火ホースが、櫓に吊られ、乾燥の作業が行われる。今でこそ火の見櫓はないから、消防署の上にある櫓からホースを吊るのであろう。私にとっても懐かしい光景である。 | ◎ | 穭田へ開け放ちたる法事の間 |
| 髙部せつ子 | |
| 忙しい農家では、祝い事や法事を、繁忙期を過ぎてから行うところが多い。この法事もあるいはそうかも知れない。その法事の間を開け放って涼しい風を引き込む、の意だけに取っては面白くない。すべての田刈りを終えて、辺り一面が穭田になった光景を、仏に見せることで、「お陰様で稲作業すべてが終わりましたよ」の報告にもなるのだろう。 | ◎ | 大文字グラスの氷鳴りにけり |
| 日高俊平太 | |
| 大文字は京都のお盆の送り火。大の字に、左大文字、妙法の文字、鳥居形、船形の五つに火が点じられる。市内の灯は一時消されるから大文字は鮮明になる。作者はどの火と向き合っているのだろう。大文字を見ながらウィスキーの水割りでも飲んでいるに違いない。その静寂の中で、グラスを口にするたび氷の音だけが、ひそかに鳴る。贅沢な時間だけが過ぎていく。 | ◎ | 鮎落つるころの瀬音となりにけり |
| 馬場 忠子 | |
| 馬場さんの住む福島県の南会津町には、只見川上流の伊南川が流れていて、鮎の名産地。それゆえ、上り鮎のころも、落ち鮎の季節も瀬音でそれが分かるのだろう。日常接する自然の移ろいが、こんな風に全て分かるのだろう。 | ◎ | 精米の糠の温もり冬に入る |
| 原山テイ子 | |
| 前句の感性が対自然へのものであるの対して、この句の感性は、長い生活の中で感知したそれだろう。玄米で持っていて、食べる前に精米できる設備などは、スーパーなどにある。その折の糠の温もりに冬を感じるというのも大切な感性である。 | ◎ | 小春日や散髪好きな父と子よ |
| 末永 淳子 | |
| ここで言う父と子とは、作者のご子息とお孫さんだろうか。その父子、休暇になると二人連れだって出かけるが、帰りが遅いなと思っていると、髪がきれいになって帰ってくる。「また床屋へ!」と家人からなじられている景だろう。 | |

