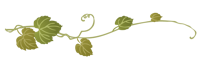
No.15 2016年9月発行
榎本好宏 選
| 今月号の「巻頭言」にも書いたことだが、季語の表記に難しいものが多過ぎる。そんな季語を歳時記から探して一句に仕立てた人はいいが、その句を鑑賞する側が、それを必ずしも読めるとは限らない。そんな経験をした人は多いはずである。加えて、私も含め年齢を重ねるに従って漢字の認知度は低くなってきている。 そんな思いもあって、俳句の一般のルールに背くことになるが、特に難しい読みの季語には、仮名を振ったら読者も助かるだろうと思っている。その試みとして、この「航路集」から、特に読みにくい季語の幾つかに、私自身が仮名を振ってみた。場合によっては、次号から、その振り仮名を増やす積もりでいる。 かつて、私の師の森澄雄は、「使い勝手のよい季語を六、七十持っているだけで十分だ」とも言った。消化しきれない季語をやたらと使いたがる人達への警告と、当時私は感じていた。その思いは今も変わらない。 今月の「航路集」の巻頭には、次の一句を選んだ。 | 影短き葵蔓の供奉の列 |
| 山口 光子 | |
| 投句葉書の通信欄に「五月に京都へ旅行しました」とあるから、葵祭とも呼ばれる賀茂祭の景を詠んだのだろう。この祭りに使われる葵蔓は、双葉葵(二葉葵とも)の葉を冠に挿したり、御簾に掛けたりして物忌みとする。一茶の句にも〈白髪にかけてもそよぐ葵かな〉とあり、葵祭には欠かせないものである。山口さんの見た供奉の列の誰の頭にも、この葵蔓が冠に挿してあるというから壮観だったに違いない。しかも、この句の手柄は、上五の「影短き」かも知れない。供奉のそれぞれの影が、真昼間の太陽のもと、自らの足もとだけに置かれている景である。とかく気張りがちなこうした祭りの景を、冷静沈着に描いたところが手柄かも知れない。 | ◎ | 葛飾のかつて鮮魚道吹き流し |
| 龍野 和子 | |
| 葛飾と言われても漠然としているので、改めて調べてみると、利根川と江戸川の下流一帯の地を指し、現在の千葉県北西部と茨城県南西部、それに東京と埼玉の東端にまたがった地域というから相当に広い。その葛飾の中に鮮魚道(なまみち)と呼ぶ街道が残っているというのだ。利根川と江戸川の下流ならば、当然のこと新鮮な川魚が運ばれたろうし、両川を通じて海の鮮魚も運ばれたことだろう。鎌倉に上がった初鰹を芭蕉は〈鎌倉を生きて出でけむ初鰹〉と詠んでいる。この鮮魚道も、銚子沖を通る初鰹が運ばれたかも知れない。季語の「吹流し」が、そんな節句のころを連想させてくれている。 | ◎ | 黴の香も樟脳の香も形見分け |
| 末永 淳子 | |
| 故人の兄弟姉妹や子供達が集まっての形見分けの景だろう。これらの人々にとって、目の前に開かれた数々の形見の品は、故人との思い出につながるだけに、それぞれの思い出話に時間をかけ、肝心の形見分けの作業は、はかどっていない。この一句のよろしさは、「黴の香も樟脳の香も」の具象表現だろう。「香」は「よい匂い」のことだが、遺族にとっては、本来「悪い匂い」のはずの黴でさえ、「香」に属する匂いになる。 | ◎ | 水貝や日のあるうちの島の酒 |
| 田中 勝 | |
| 水貝とは鮑料理の一つで、生鮑の表面に塩を振り、硬くなった鮑を薄く切り、うすい食塩水に氷を浮かせて食べるぜいたくな料理。北海道料理として知られるが、北海道の離島に渡り、その土地の名酒を飲みながら日のあるうちから、この料理をもてなされたという。三年余、北海道に在勤した私も、天売島でこの料理を食べている。 | ◎ | 母を訪ふならひ林檎の花の頃 |
| 児玉 一江 | |
| 林檎は晩春のころ、白い五弁の花を付ける。お母さんが住んでいるところが、青森や長野といった林檎の産地だとすれば、深かった雪も消える時分に当たる。結婚したばかりのご主人と一緒だったり、よちよち歩きの出来るようになった子供を連れて行ったりもした。それらがすべて、林檎の花と、母親の笑顔につながることだったに違いない。 | ◎ | 青蘆の丈に風音変りたる |
| 宮下とおる | |
| 蘆はどこにでも生えているから、屋根をふいたり、簾にしたり、漢方薬の原料にもなっている。その青蘆の密生している川辺を歩いていると、草丈の高さによって、風音の違うことを発見したのだ。昔は「あし」と読むと「悪し」につながるので、善につながる「よし」と言った時代もあった。 | ◎ | 後れ毛の吹かれやすさよセルを着て |
| 船杉しん子 | |
| 単衣着物地のセルは、初夏の更衣のから着用した。軽くて、肌ざわりがいいところから、普段は感じない後れ毛さえも微妙に感じるというのだ。このセルなる言葉も、だんだん聞かれない時代になってきた。 | ◎ | 祭笛腰にたばさみ切火受く |
| 安田みつる | |
| この句の主人公は、夏祭りの囃子方の笛吹きなのだろう。まず神職から、おのおのが切火を受けたのだろうが、手にした笛を脇にはさんで、神妙にしているさまが、読者にはよく伝わってくる。 | ◎ | 郭公や水田に居久根浮かぶかに |
| 太田 直史 | |
| 東北地方では、屋敷林のことを居久根(いぐね)と呼ぶ。一面に田に水が張られると、それまで目立たなかった居久根が島のように浮いて見えるのだろう。そのころ、渡来したばかりの郭公が鳴き始めたのだ。 | ◎ | 紙雛鋏の音の中に生る |
| 栗城 郁子 | |
| こういう鋏使いの名人がいる。一枚の紙と鋏を手にした名人は、鋏の音をさせながら、たちまち紙雛を作った。ちょうどこの日は、雛祭りの日だったのかも知れない。 | |

