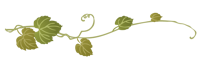
No.36 2020年3月発行
榎本好宏 選
| ここ二、三十年になろうと思うが、「景に会するは遠きに在らず」の漢詩の一節を私の信条としてきた。つまるところ、寒紅梅が見たくば、小田原の梅林に行かずとも、近くのとあるお宅の庭に咲く寒紅梅から、その景を想像すればよかった。この寒中も、自宅から数分の家々の庭先にある千両や万両からいろんな景を拝借できた。 千両、万両が出たついでに言えば、かつて、長い療養から帰った師・森澄雄は、わが庭を見ながら、 わが庭のもの千両も万両も と詠んだ。悪いことに、この後寝づくことになった部屋のベッドより見える風景から、すべてが見えると言いながら、大景の句を作り続けた。この辺りが、私の信条「景に会するは遠きに在らず」の手本だったのかも知れない。 今月の巻頭には、次の一句を迷わずに選んだ。 | 運ばれてゐる間も跳ねて燻り炭 |
| 太田かほり | |
| まだ炭火に燃料や暖房を頼る時代の話をすれば、一般のお宅の朝は火熾(おこ)しから始まった。それら沢山の炭火を七輪から、火鉢、炬燵へと順次配って歩く光景が、この一句の舞台に似ている。熾したての炭は爆(は)ぜながら燻(いぶ)りながら、家中に炭の匂いが漂った。 とまで書いたが、この一句の世界はこんな場面ではあるまい。想像できる一場として思い描けるのが茶席の一場面かも知れない。茶席の準備のため賄い所で炭火が熾され、その炭が茶席に運ばれる道筋の光景であろう。辺りに炭の匂いが漂う中、一筋炭の熾ぜる音もしてくると思えば良いのかも知れない。 もう一句、 脇役といふ消炭のやうなもの の「やうに」の比喩の句も関心を持ったが、どこか私が常套としてきた直喩の方法に少し似過ぎているとも思える。 | ◎ | 茶を点ててもらひぬ十二月八日 |
| 上春 那美 | |
| 昭和十六年以前に生を受けていなくとも、あの戦中、戦後の辛い時期を送った人達にとって「十二月八日」の五文字は重い。ただ、終戦の日から数えても七十五年経った今では角川版の大歳時記にもあるような〈開戦日くるぞと布団かむりけり〉という激しい思いはとうに沈潜させているが、この一句の中にも、その沈潜の奥に反戦の堅い礎がのぞけるのである。私の三十年も前の作品にも、〈十二月八日よ母が寒がりぬ〉があるが、あの戦争で父を亡くした私の恨み節も込められている。 | ◎ | 寒柝の戻つてきたる鳥居前 |
| 児玉 一江 | |
| 冬の寒い夜に拍子木を鳴らして回る寒柝は、今でも続いているのだろう。この季語を見ると私には、山口誓子の 水枕中を寒柝うち通る の名句が思われる。寒柝の一団の集合場所は、神社の鳥居前の外灯の明るい場所だったのだろう。そこから、懐中電灯の明かりを頼りに路地にそれぞれ散っていくが、各々が打つ拍子木の音が、神社の杜にこだまして反ってくる。そんな各一団がまた元の鳥居前の灯の許に戻ってきたのだ。 | ◎ | 冬満月濤音の路地みな海へ |
| 赤木 和子 | |
| この風景は私も好きな漁村風景である。海辺の傾斜地の細い路地に、判で押したように漁師の家が軒をつらねて並ぶ光景である。その小路の軒下に洗濯物が干され、植木鉢が並んでいる──というのが、私も好んで通う路地である。その小路は全て海へつながり濤音が聞こえるが、その先に今日は冬満月が昇ってきたという場面である。シルエット状の軒並みと月光の対比が見事と言える。 | ◎ | 除雪機の鍵の番号誕生日 |
| 佐藤 耐子 | |
| 偶然手にした電車の切符の番号とか、目の前を通り過ぎる遊覧船に書かれた数字が、自分の誕生日や電話番号と同じだったりすることがある。人に言うことではないが、自らニヤッとすることになる。佐藤さんは自らの除雪機をこれからの雪に出している折、自らの誕生日と同じ鍵の番号であることに気づいた。私の言う電車の切符や船の番号と違って、この一句には生活感を伴った季節感が見事に出ている。 | ◎ | 初暦いつもの釘に掛けにけり |
| 佐藤 享子 | |
| このお宅では大晦日に、古暦を外し新暦に掛け替えるのだろう。毎日のように暦とは目を合わせているのに、釘との出遭いは一年ぶりのこと。何でもないただの釘だが、こう書かれてみると新鮮に思えてくるから不思議である。 | ◎ | ものたらぬ五日の居間のがらんどう |
| 目黒 礼 | |
| 目黒礼さんは料理上手で接待上手。正月の四日までは居間は賑わったに違いない。しかし五日ともなると客足も途絶え、さしもの目黒家の居間もガランとなった。もてなし上手の一種の空虚感だろうか。 | ◎ | 鯨汁話してみやう明日また |
| 角野精三郎 | |
| 鯨の脂肪分の多い肉を具にした味噌汁が鯨汁。昔から煤払いの夜食べることになっている。あまりに美味だったので、ある席で話したら大いに受けた。それなら明日も話してみよう……という仕儀になった。 | ◎ | 冬銀河今なら父に言へるのに |
| 花村 美紀 | |
| かつての父親は厳しかったから子供、ことに娘にとって辛い存在だった。しかし自分も父の齢になって、その立場が分かった。冬銀河と向き合った自分の立場も。 | ◎ | 年毎に小さくなりぬ鏡餅 |
| 吉田 一男 | |
| 大家族だったころは大きな鏡餅をしつらえたが、祖父母がいなくなり、子供が一人去り、二人去りして、年々鏡餅も小さくなっていくのだろう。 | |

