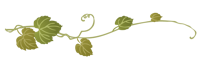
No.21 2017年9月発行
榎本好宏 選
| 私達が子供の頃は、「雷が鳴ると梅雨が明ける」と言い、梅雨明けを心待ちにしていた。しかし、近頃の梅雨は様変わりしたようで、九州の福岡、大分辺りでは集中豪雨で数十人の死者、行方不明者を出しているが、雨の少ない埼玉の河川では例年の十分の一しか雨が降らず、用水の制限が始まっている。 これらの原因が地球の温暖化によるものだと分かっていながら、ほとんど対策が取られていない。二、三十年先の我々の生活はいったいどうなるのだろうか、案じられてならない。 さて、今月の巻頭だが、迷わず次の一句を選んだ。 | なにがなし遠目となりぬ麦の秋 |
| 早野 和子 | |
| 現在の麦の秋の感覚は、竹の秋などと同じように、黄ばんだ視覚からだけの意味しか持たないが、本当は麦が黄ばんだ時に発する、あの熟れる匂いも含まれている。私と同年代の早野さんも戦後の米の足りないころ、米に混ぜて炊く大麦や、メリケン粉不足を補うため沢山蒔いた小麦などが、六月頃、あのさわやかな匂いを辺りに漂わせたことを知っているはず。だから、匂いも麦の秋の語感となっている。 早野さんの作品に添っていえば、「なにがなし遠目となりぬ」の文言は、終戦直後のあの不安定な時代を少しでも虚に託したい思いの現れだったのだろう。仮に近くのものに眼差しを向けるとすれば、目を覆いたくなるようなうつつがある。自ずと早野さんの日常は、この遠目で救われてきたのかも知れない。少し過剰鑑賞をしたようだが、同世代にとって、そう思えてならないのである。 | ◎ | 雨乞いと決めて男は早仕舞 |
| 渡部 華子 | |
| 渡部さんの投句葉書の通信欄に、今日は梅雨晴間で暑く、畑は草が伸び困っている。そろそろいろんな野菜の種を蒔かなくてはいけないのに―といった事が書かれてあったから、この一句の雨乞いも実感として伝わってくる。その雨乞いも、滝に牛の首を投げ入れ竜神の怒りをかうような大仰なものでなく、社殿や堂宇にお籠りして祈願するようなものであろう。その雨乞いに出ていく男達を見送る女性方の祈るような思いが、この一句から伝わってくる。不思議なことに、この原稿を書いている七月十八日の昼のニュースで、奥会津の只見町と金山町は町民の退避命令が出るほどの大雨に見舞われたとあったから、渡部さんの住む隣町の南会津も雨に見舞われたことだろう。 もっと不思議なことは、この原稿を書き始めた午後二時ごろ、滅多に雷など鳴らない、私の住む横浜市に雷鳴がとどろき大雨が降りだした。その偶然さに、ただただ驚いていた。 | ◎ | あやめ舟花より低く巡りけり |
| 安部由美子 | |
| あやめと言えば、誰もが陸から見下ろす花と思いがちだが、作者は舟の中からこの花を見る機会に恵まれた。普通の人ならそんなことも感じないだろうが、俳人の安部さんは「花より低く巡りけり」と把握した。単純なようだが、これは大発見と言っていい表現である。大事なことは、固定観念にとらわれず、この句のように心をいつも対象に開いておくことだろう。 | ◎ | 泰山木の花を居久根の目印に |
| 富田 要 | |
| あまり見かけない居久根(いぐね)なる言葉は、屋敷林のことだったり、防火や防風のため、隣家との境や屋敷の周りに植えた木を言う。主に東北地方でこう呼ばれている。この一句の景は前者であろう。その居久根の中に、今ちょうど花を付けている泰山木が見たくて作者はやってきた。久根とは垣根のようなものを言うが、戦時中私が疎開していた群馬では、「樫ぐね」と呼ぶ風除けが北側から西側にかけて植えられていたが、これは真北の赤城山から吹きおろす赤城颪を防ぐためのものだった。 | ◎ | 夕明り田植終えたる静けさよ |
| 見高美代子 | |
| 米作りには八十八回の手間がかかると言われてきたが、今では機械化が進み、だいぶ楽になったはずである。とはいえ、一番大切な田植えは、田面がいっぺんに賑やかになる。一日の作業を終え、機械や農具が片付けられ、人々が田から引き揚げると、この句の言うような静かな景になる。折からの夕明りの中に漣が立ち、やがて蛙の声も聞こえ始める。 | ◎ | ところてん裸電球低くあり |
| 山口悠紀子 | |
| こんな一句を見せられると、つい童心にかえってしまう。ところてんを注文すると、井戸水か、裏山から引いてある水より取り出し、突いてくれる。私のいた群馬では、酢じょうゆの入った瓶の口には青い杉の葉が挿してあり、瓶を逆さに振ると適当な量の酢じょうゆが、ところてんに掛かる。不思議なことに、この地方では一本箸でそれを食べる。ところてんの漢字は、「一心太助の臍」と小学校の先生に教わった。その心太は、季語として「こころぶと」とも読む。 | ◎ | 鱚を買ふある日の立子由比ヶ浜 |
| 宮下とおる | |
| 鎌倉に越してきた高浜虚子や星野立子は、由比ヶ浜に程近い借家に住んだ。家の真ん前を江ノ電が走っている。今も旧居跡の生け垣の隅に、立子の小さな句碑が建っている。江ノ電の線路を渡り数分で海へ出るが、この辺の漁師から、立子が鱚を買ったのだろう。その夜の虚子庵の句会のあと、たぶん鱚の塩焼きか天ぷらが出されたと思いたい。 | ◎ | くわくこうに目覚むることもみちのおく |
| 石井 文子 | |
| 石井さんは在京中、長いこと町屋の私の講座に通ってきてくれていたが、数年前、古里の岩手に帰られた。その石井さんの朝の目覚めは郭公の鳴き声だというから、何ともうらやましい話である。 | ◎ | 禰宜老いて祝詞つまづく山開き |
| 秋丸 康彦 | |
| 作者がワンゲルの会のリーダーであることは聞いているが、このグループ、山開きの日には毎年同じ山に登るのだろう。当然のことながら儀式をする禰宜さんとも顔なじみだから、祝詞を聞きながら、「年をとったな」と思ったに違いない。 | ◎ | 螢火の方へはうへと人動く |
| 三浦 郁 | |
| 螢は群れて飛ぶ習性があるから、つい人々はそちらに向かって移動する。懐中電灯などをつければ不粋だから、足許の不安に気を配る人影が群れて動く様子が見えてくる。 | |

