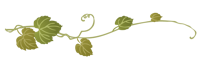
No.35 2020年1月発行
榎本好宏 選
| 新年号だから書く訳でもないが、私の子供の頃のお節料理用の箸は「太箸」と決まっていた。折れることを忌み嫌って太く作られたからこう呼ぶ。 太箸のたゞ太々とありぬべし と、高濱虚子も詠んだこの箸、柳の白木で作るところから柳箸とも呼ぶ。こんなことを想いつつ航路集の選を終えた。 その新年号の巻頭に次の一句を選んだ。 | 銀杏を拾ふ守衛に会釈して |
| 石井 公子 | |
| 秋になって梅干しの粒々のように、地面を埋め尽くす銀杏を見ると、つい拾って持ち帰り干し銀杏を作りたい思いにかられる。この作者の場合も、毎年銀杏を拾う場所が決まっていて、そこで拾った一品で干し銀杏を作るのだろう。 〝守衛〟とあるから、寺や神社のように普段自由に出入りできる場所でなく、例えば美術館のように時間限定で開放される場所が想像できる。温かい眼を向けている守衛さんに、「今年もまた戴きます」と言わんばかりの会釈をしたのだろう。両者の間に通う微妙な優しさが見事だ。 | ◎ | 時雨傘芝居観る間に乾きけり |
| 露木 敬子 | |
| 時雨の季節の外出は厄介だが、それも芝居見物とあれば、さして気にも掛かるまい。その芝居も顔見世興行のものだったら、むしろ晴れがましい思いで出掛けられたことだろう。顔見世とは歌舞伎の興行用語で、江戸時代、各劇場が十一月から一年契約で役者を雇う制度だった。その制度が明治以降も残り、現代でも京都の南座には十二月になると俳優の名を書いた「まねき」が挙がる。折りから外は時雨模様。芝居を観終えた喜びとともに、傘の乾きも嬉しいことである。 | ◎ | 炬燵出すけふ癸の水曜日 |
| 柏倉 清子 | |
| 火を扱う生活用具を出したり蔵ったりする折りは、いちいち縁起かつぎの言葉が使われた。例えばこの一句のように、火の用心を心掛けなくてはならぬ日は、慎重に選ばれた。まず「癸(みずのと)」という日である。少々ややこしいことだが癸は十干の十番目、五行説によって五行の水に十干の癸を配したもの、となる。砕けて言えば「水」ゆかりの日でもある。加えて火曜日だったら大変なことになるが、そこは水曜日で落ち着いた。 | ◎ | 台風一過地上の影のみな尖る |
| 木村 珠江 | |
| 去年の夏から秋にかけて、関東地方はいくつかの台風に襲われ大きな被害を受けた。中でも第十九号による被害は甚大だった。その嵐の去った後、葉が散り地上に残され木々の影だけでなく、写る影のすべてが尖って見える──というのだ。その「尖り」の感覚の中に、秋から冬にかけての美感がほのかに込められていようか。 | ◎ | 胡麻叩く後ろ姿を己とも |
| 太田かほり | |
| 胡麻の木は上向きの莢の中にびっしり実を結ぶので、物に立てかけて乾燥させる。ただし収穫の折りは逆さに握り棒で叩いて胡麻の実を取る。この過程を知らない人には、その仕草は判然としない。ましてや後ろ姿たるや……。一種の自画像とも思える。 | ◎ | たぐることうれし触れもし烏瓜 |
| 赤木 和子 | |
| 烏瓜は実が青いうちは木々に埋没していて見えないが、赤らんでくると目立つ。つい蔓の端をつかんで引いてみると、思ったより多くの実が手許に引き寄せられる。そしてすぐ触ってみたくもなる。更に嗅いでみたかも知れない。 | ◎ | 秋扇たためば月日遠ざかる |
| 髙部志づの | |
| 秋扇という季語の語感には、心なしか、開いたり閉じたりはするが、風を送る動作は伴わないという意がある。そして晩秋、扇は閉じたままとなる。更に、この人の内に連綿と続いていた時間は、一瞬にして空虚なものになったのだろう。 | ◎ | 数へ日や路地の真砂女の下駄の音 |
| 真下 忠男 | |
| 鈴木真砂女の店は、銀座の稲荷横丁にあり、私もよく通った。九十歳を越えても元気だった真砂女は〝銀座の三婆〟とも呼ばれながらも、この路地で客を見送ってくれもした。 | ◎ | 枯蓮八橋のごとつながりて |
| 蓮井美津子 | |
| 池の面に枯れ始めた蓮が、さながら八橋のように連なっている──の句意だが、私には八橋の言葉から、尾形光琳の「八橋図屏風」の絵柄が想像できる。 | ◎ | 虫の音をたんと貰うて誕生日 |
| 安部由美子 | |
| 静かな秋の夜、誕生日を祝ってもらったのだろう。「たんと」の俗語が面白く使われた一句かも知れない。 | |

