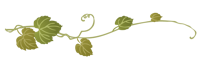
No.29 2019年1月発行
榎本好宏 選
| 平成最後の正月と思うと、また心も改まる。かつて周囲にいた年配者から、「私も明治、大正、昭和の三代を生きてきたから……」などという言葉を聞くと、特別な感慨を持ったが、間もなく変わる新しい年号になると私も同じ台詞を口にすることになるかも知れない。これを読んでくれる多くの仲間も、私と同じ感慨を持つことだろう。そんな思いにつながる次の一句を、今月の巻頭句に選んだ。 | 余生いましをりのやうにわれもかう |
| 小谷迪靖 | |
| 「余生」という言葉には一種の差別感があるから、自らに言うのならともかく、他人に対していう言葉ではない。しかし、この「余生」と自らに使った小谷さんの語法にはまず温かさを覚える。そして中七から座五にかけても、「余生」の言葉に適うように仮名書きにしたこともまた一工夫かも知れない。 その仮名書きの「しをり」にも多くの意味を感じるが、私は、本の間にはさんで使うあの「栞」と思いたい。ある日作者は偶然、吾亦紅の花に出遭った。そして立ち止まって向き合う。その一つさえ余生の中の大事な一つだと思ったに違いない。もう少し過剰鑑賞をすれば吾亦紅の文字づらは「吾もまた紅いんですよ」の意にもとれ、そうした自己主張をする花にさえ、作者は余生の一頁にはさむ。こうした余生が、どれだけ豊かなものになるだろうかと、同じ余生の身にある私もつくづく相槌を打ちたい。 | ◎ | 人文字の列のひとりや鰯雲 |
| 大須賀衡子 | |
| 学校の校庭かグラウンドで描いた人文字なのだろうが、どんな人達が、何のために、一体どんな人文字を描いたのだろうか。という常識的な興味より、人文字をズームアップすれば、文字を支える人々の声や顔の表情までも見えるが、レンズを戻せば、その「生」は単なる「物」に置きかわる。しかし、人文字を構成するおのおのからは、秋特有の鰯雲が一天にひらけるだけである。人文字の持つこの「生」と「物」の両者が見えるのは「列のひとり」という言葉の働きなのかも知れない。 | ◎ | 掛大根外し村中軽くなる |
| 柏倉清子 | |
| 作者の住む福島県の奥会津は、農業の盛んな土地で、雪の多い所でもある。当然大根も冬の間の大事な作物だから、大根を掘って、洗って、干す作業は雪の降る前の大作業である。しかし、その大根は重い。私がこの奥会津で見た光景の一句に〈母背負ふやうに大根を干し場まで〉(句集『青簾』所収)があるが重労働である。そんな経験を村の誰もが持っているから、大根が干し上がって外された風景は、視覚的に見えただけなのに村中が軽くなった、と作者には思えたのだろう。 | ◎ | 田仕舞や本家分家の順ありし |
| 松岡郁夫 | |
| 都会地に住んでいると分からないが、地方には本家と分家の在りようが今でも続いているようであり、この一句もその例の一つだろう。田仕舞は秋収めとも言って、稲を刈り、米を俵に詰めるまでの、秋の農作業の一切を終えることをいう。ところが、本家、分家制度の厳しい土地では、まず本家の作業を分家も手伝い、しかる後、分家も自らの田仕舞になるという仕組みになっている。この一句はそのことを言っている。 | ◎ | 墨継ぎのやうにつくつく法師かな |
| 坂本洋子 | |
| 蟬の鳴く季節と鳴き声はいろいろだが、声が聞こえると、つい耳を傾けたくなるのが法師蟬かもしれない。また、油蟬のように声を聞いて見上げるとすぐ姿の見える蟬と違って、姿はなかなか見とどけられない。その法師蟬の鳴き声を書の墨継ぎになぞらえた比喩は、みごとというほかはない。この一句に引き込まれながら、ではどんな筆だろうと思ってみると、私には太筆より中細の筆が想像でき、墨が枯れ始めたところで一息入れ、墨を継ぐ場面を思ってしまう。巻頭句同様に比喩がまことを言い当てたとしか言いようがない。
| ◎ | ほほづきを灯としたる夫よ来よ |
| 上春那美 | |
| 盂蘭盆会が近づくと、仏具店などだけではなくスーパーにも鬼灯が店先に並ぶ。仏の多いわが家でも必需品で、枝付きのまま仏壇に飾る。上春さんは、何年か前にご主人を見送っている。そのご主人が仏前の鬼灯を灯としてこちらにやって来て欲しいと願う。もう二十三年前に妻に先立たれた私も、つい首を縦に振りたくなる。 | ◎ | 流鏑馬の一の矢紅葉散らしけり |
| 高部志づの | |
| 馬を走らせながら矢を射るのが流鏑馬だが、有名なのは鎌倉の八幡宮で行われるもので、私も見たことがある。境内の参道を横切るように、流鏑馬用の道があり、当日は道の両側が人で埋まる。馬上から振り返りざまに矢を射る大景と、ほとんどの人が気付かない紅葉の散る小さな景の組み合わせが面白い。 | ◎ | 寿福寺の門開いてをり年尾の忌 |
| 山本たか子 | |
| これも鎌倉の一句。寿福寺は高浜虚子、子息の高浜年尾、長女の星野立子などの墓のある寺で知られる。その寺の門が、この日が命日の年尾の法要のため門が開かれているのだろう。「ホトトギス」系の人達が列をなして門内に入っていく様子も見えるようだ。 | ◎ | 草の絮吹いて別れの挨拶に |
| 末永淳子 | |
| ごくごく親しい間柄の知人との別れの場面だろう。別れの立ち話をしながら、辺りに生えている草の絮を抜いて、分かれる相手の顔に吹きかけたのかも知れない。そのささやかな行為の中に滑稽味が生まれた。 | ◎ | おしろいの花や誰彼帰るころ |
| 蓜島良子 | |
| 主婦は雑事に追われ、気づいてみるともう夕方近い、ということが多い。そんな時刻に気づいたのは、夕方になると咲く白粉花を見たからだろう。作者はそれまでかかわっていた事への思いから一変、この先次々に帰ってくる家族のことを思うようになると、私には読める。 | |

