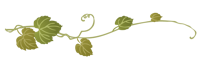
No.37 2020年5月発行
榎本好宏 選
| のっけから妙な言い方になるが、今月号の「航路集」の選をしていて強く感じたことは、「取り合わせ」の作品が少なく、仮にあっても、取り合わす季語と事柄の間に感性が働かず、どちらかと言うと知恵の斡旋が目立つことでもあった。例えば取り合わせの代表句 鰯雲ひとに告ぐべきことならず 加藤楸邨 紺絣春月重く出でしかな 飯田龍太 の二句に言えることは、季語と事柄の間に、知恵とは違う感性が働いていることであろう。 この方法は、「二句一章」とか「二物並列」などとも呼ばれ、まず一番大事なことは、作句の折に考えることより感ずることを大切にしなくてはならない。鑑賞する場合にも、なぜこの句が好きか嫌いなのかを思うのでなく、〝なぜ〟の思いを外し、単純に好きか嫌いかだけで向き合うと、自らの中の感性にも出遭えることになる。 そんな思いで「航路集」の今月の巻頭には次の一句を選んだ。 | 棟上げの近き槌音つばくらめ |
| 金子智枝子 | |
| 自分の住む家を新築する人の一つの区切りは棟上げの日をどう迎えるかでもある。上棟式には棟の上から餅などを撒くかも知れないし、ご近所に祝いの品々を配るかも知れぬ。そんなことどもを案じながら、棟上げの進行が日々気になるはずである。一方の大工さん達も、棟梁の指揮のもと、棟上げを目指し、おのずから打つ槌音にも力が込められる。そんな時節を、別名で初燕の名の燕がやって来て辺りを舞う晴れがましさがある。 「棟上げ」以下のフレーズと、季語「つばくらめ」の間には何の関連性もないが、並べて置かれてみると、何とも言いようのない爽やかな情感が漂う。この不思議を解釈せずに嗅ぎ取ることこそが「取り合わせ」の妙である。もっと言えば、この両者の間に顕(た)つ雰囲気に対して、「好き」か「嫌い」の反応だけで十分であろうとも思う。 | ◎ | 梅一輪息つぐもののみな光る |
| 赤木 和子 | |
| この一句も、言ってみれば「取り合わせ」の一句である。季語の梅一輪と、それ以下のフレーズの間に微妙な情感を湛えている。作者が待ちに待っていた梅に一輪花が咲いた。その花から作者は、万物を生育する天地の精とも言える「気」を貰った。その「気」をもって辺りを見回してみると、梅に近い頃に花を付ける植物はもちろん、木々の新芽などすべての「息つぐもの」が光っていると見立てる。巻頭句の少し離れた「取り合わせ」と違って、取り合わせた両者が終(つい)には一体化して一つの美学になる妙が、この一句にはある。 | ◎ | 雛の軸解けば亡父の背高かりき |
| 平峯 秀子 | |
| このお宅では毎年雛の日に、雛の絵の描かれた軸が床の間に掛けられるのだろう。その軸掛けは毎年変わって、娘さんだったりお母さんだったり、時には興味を示す息子さんだったりする。だが、その誰もが軸を掛ける釘の高さに難儀する。そんな折り必ず誰もが口にする言葉が「お爺ちゃんなら踏み台を使わずに届いたのにね」と亡き祖父を懐かしんだ。
「亡父(ちち)の背高かりき」の一言は、雛の節句にこの家で呟かれる家宝のような言葉なのだろう。 | ◎ | 天上の野がけの妻へ玉櫛笥 |
| 小谷 迪靖 | |
| 小谷さんの周辺を少し存知あげているから書けるのだが、小谷さんは十年ほど前に令夫人を見送り、昨年だったかに、奥さんが大事にしてきた遺品を整理されている。その奥様へこの春、玉櫛笥(たまくしげ=美しいくしげ)を贈ったというのである。この句が私を感動させたのは、「野がけ」の言葉だったかも知れない。春や秋ののどかな日に、食べ物などを用意して野山で遊ぶことを野掛け遊びとか野遊びと呼ぶが、語感として野遊びでは俗に落ち過ぎる。小谷さんの妻恋いにはやはり「野がけ」が適っている。 | ◎ | 鍬のまへ鍬のあとへと初燕 |
| 佐藤 享子 | |
| 初燕がやって来た。丁度田畑の耕しのころである。その耕しの鍬の前に現れたり、後ろを低く舞いながら初燕が飛ぶ。この句に関心するのは「鍬のまへ鍬のあと」の表現かも知れない。こう書くことで、前と後ろの空間が描かれ、しかも前から後ろへ移る時間も表現できた。私の師、森澄雄の言葉を借りれば、「俳句は時空の文芸である」の一言に適っていようか。 | ◎ | 水音のかすかに雀隠れかな |
| 原山テイ子 | |
| 季語だから改めて書くまでもないが、春になって草木の葉が伸び雀が隠れるほどになる景が雀隠れ。こんな草むらは、寝転ぶのに格好だが、大方は小さな流れがひそんでいて、この句のように、水音がかすかにしているものである。 | ◎ | 炭継ぐや師に習ふことまだありて |
| 林 わこ | |
| 「炭継ぐ」とあるから、師とは茶道の師なのかも知れない。炭を継ぐ折りの、あの少々軽いながら乾いた音を聞きながら、この師から学ぶことは未だ沢山あると、自らに言い聞かせているのだろうか。師が茶道の師でないとすれば、この句も巻頭で触れた「取り合わせ」の別の機能が働いてくる。 | ◎ | 冬帽と鮒竿入れて棺閉づ |
| 田中 勝 | |
| 亡くなった方の出棺の前の景。棺を閉じる間際に故人の冬帽子と好んで使っていた鮒竿を入れた。鮒という魚は一年中獲れるが、食用にする場合は冬が一番旨いとされる。案外死の直前まで冬鮒釣りの準備をしていたのかも知れない。 | ◎ | 桜餅ゆつくり剝きぬ聞き上手 |
| 馬場 忠子 | |
| 桜餅の葉をゆっくりはがしながら、相手の話をゆっくり聞くとなれば誰もが念じていながらできないことである。この句の中にもゆったりした時間がながれている。 | ◎ | 囀や菓子の木型に餡を置き |
| 花村 美紀 | |
| 人間誰もが持っている五感の感覚から言えば、菓子作りの嗅覚、触覚に、更に囀の聴覚が加わり一句が膨らんだ。 | |

