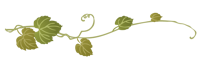
No.26 2018年7月発行
榎本好宏 選
| 「『航』のこころざし」(本誌の扉)に書いた、「おのおのが持つ、無意識下のやわらかい自己の発現をめざす」は、心に顕ちてくる思いを、頭脳を通過させて智恵を加えずに、自らの心の持っている生の言葉で表現したい―というのが狙いでもあった。言葉が難しすぎるのか、この「こころざし」に適った作品にほとんど出会っていない。もう一度書こう。「智恵は俳句にとって大敵」なのである。 今月の「航路集」の巻頭には、次の一句を選んだ。 | 行く春や仏堂のみな半開き |
| 早野 和子 | |
| 寺々の蔵する物の中には、何百年もの時を耐えてきた宝物が数多くある。これらを安全に保持するための行事「虫干し」も季語にはあり、傍題季語として「虫払ひ」「土用干し」「曝書」「風入れ」なども並ぶ。これらは、古くから禁中で七月七日に行われてきた蔵人が御物を払う定めにならったものだが、その行事は中国でこの日に曝涼を行うしきたりを取り入れたものである。 しかし、寺に伝えられる宝物の多くは、こうした儀式ではとても守れない。季節ごとに温度や湿度や風といった日常の自然に対応していかなければならない。例えばこの句のように、行く春ともなれば仏堂の扉を半開きにして、少々湿度は高いかも知れないが、暖かい風を堂内に吹き入れなくてはならない。そんな僧達の修行の日常までもが、この一句の「半開き」に読み取ることができよう。 | ◎ | ゲレンデの名残の筋や田水張る |
| 石井 文子 | |
| スキー客でにぎわったゲレンデの雪も融けて、もとの棚田の地面が現れると共に、田作りの作業が始まった。もちろん雪場だから田水も豊富で、田面はたちまち水に満たされていく。ところが、ゲレンデとして使った場所には、スキーのエッジを立てて滑る急斜面のコースがあったのだろう。雪が消えた後も田の畦に、エッジで削られた個所が残っていて、その修復に手間どっているのかも知れない。「名残の筋」も、その現実を素直に受け入れている優しさがある。 | ◎ | 啓蟄や錠前渋き農具小屋 |
| 髙部せつ子 | |
| 二十四節気の一つである「啓蟄」は、現代の暦に当てはめると三月五日ごろになる。ちょうど冬籠りの虫が地に這い出るころに当たる。となれば、季節的には農作業の始まるころと一緒になる。冬の間農機具を仕舞い込んであった小屋を開けようと鍵を差し込むと渋い音が立ったという。そう、秋の収穫後には使っていなかったからである。そこで作者は、秋の農耕を終えてからの「時間」を思ったに違いない。 | ◎ | 矢車の音に晴れゆく甲斐信濃 |
| 田中 勝 | |
| 夏にはいろんな風が吹くが、冬の季節風が止んでオホーツク海高気圧が発達し始めると「やませ」なる風が吹き始める。ちょうど鯉幟を揚げるころでもあるから、この一句の「矢車の音」の季節でもある。そんな時節に、作者は山梨から長野にかけて散策したのであろう。その道中、山から吹き下りる「やませ」が矢車を吹き鳴らしている。しかもこの風につれて、いずれの地も晴天が続いているというのだ。 | ◎ | 早々に糶の仕舞ひや初鰹 |
| 松岡 郁夫 | |
| 古くから「褞袍質に置いても初鰹」の諺があるように、初鰹は初夏の待ちに待った魚でもあった。もちろん、今でもそうである。解禁と共に市場で糶にかけられる鰹は、あっという間に買い手が殺到して売り切れる。そんな糶の様子を見ていた作者は、「さもありなん」と思ったに違いない。 | ◎ | 利尻昆布けむりのやうに削られぬ |
| 花村 美紀 | |
| 北海道の利尻昆布や日高昆布は、出し昆布としては現地から出荷されたが、昆布の加工品はほとんど大阪で加工されてきた。この一句は「とろろ昆布」の加工の様子であろう。今は、乾いた昆布を機械で削るのであろうが、かつては昆布を鉋で削った。私も見たことがあるが、大工さんが薄く削る板屑のように、鉋から吹き出される。「けむりのやうに」は、これを言ったのであろうが、適切な比喩になった。 | ◎ | 樹木医の大きな鞄花は葉に |
| 齊藤 眞人 | |
| 私も詳しくは知らなかったが、樹木医の制度は林野庁の補助事業として、二十数年前に生まれた。特に大きい木を対象に、薬剤の散布や塗布、老朽化した枝や幹の切断などを行うのだという。その樹木医が、花の盛りのころでなく葉桜のころに、それも大きな鞄を提げて桜の木の下にやってくるというところに、どこかユーモアがこもる。現代俳句から消えかけている滑稽味あふれた一句になった。 | ◎ | 潮待ちの桶に肘置く鮑海女 |
| 佐藤 享子 | |
| 潮が引くのを待つのか、満つるのを待つのか素人には分からないが、鮑採りにふさわしい潮かげんを待っている海女の様子は分かる。その待つ仕草がふるっている。浮かせた桶に肘を乗せているというのだ。言い得て妙である。 | ◎ | 穀象や昭和を生きて影もたず |
| 秋山田 京子 | |
| 若い人には理解してもらえない穀象虫だが、戦中、戦後の米のない時代の国民は、この虫に襲われて難儀した。「昭和を生きて影もたず」の解釈も難しいが、小さかった作者の耳に、「また、穀象にやられた!」なるお母さんの大声だけが、昭和の歴史の一部として残っているようだ。 | ◎ | 春耕の畝黒々と雨上がる |
| 目黒 礼 | |
| 雪消えを待って耕された田に、畝もきちっと立てられた。見渡す限り早春の景である。そこへ春の雨が降った。改めて見やると、土を盛った畝だけが黒々とした線に見える。こんな微妙な変化もまた農業の楽しみの一つであろう。 | |

