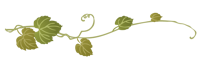
No.34 2019年11月発行
榎本好宏 選
| 今月のこの欄の選をしていて感じたことが二つあった。一つは作句の大原則でもある「いかに言うかではなく、いかに言わないか」の約束が守られていないことだった。言いたいことを一つ伏せることで、それが一句の世界になる。逆に全部書いてしまうと散文の世界になり俳句でなくなってしまう。 もう一点は、投句の中に吟行句が多いせいか、「どこそこで何を見てきました」的に報告の作品が多いことでもあった。中でも目に見た、つまり視覚の句が目立つ。人間には視覚も含めて、聴覚、味覚、嗅覚、触覚の五感があるが、これらをも動員して句を作ると、作品に深みが生まれるはずである。 ――今月の巻頭には、その意も含めて次の一句を選んだ。 | 栂尾涼し洛中は陽まみれらし |
| 三枝美智子 | |
| 栂尾(とがのお)と言えば改めて書くまでもなく、京都の高尾、槇尾(まきのお)と並んで三尾(さんび)と呼ばれる紅葉の景勝地でもある。また、ここには名刹、高山寺があるから、この寺へ行く道筋の一句であろうか。 夏とはいえ、この辺りまで来ると秋を感じさせる涼しい風が吹き、辺りの木々の葉を揺らしているころだろう。しかし、空を見上げると夏日が厳しく暑そうな日差しがそそぐ。木々に取り囲まれているから、ここからは見えないが、辿ってきた京都の中心地、洛中は、さぞや日盛りで暑いことであろうと思う。 涼風に居ながら思う触覚の感覚と、炎天から感じる視覚の感覚が相重なって、しかも読者に、時間と空間の豊かな景を提示してくれている。 もう一句の〈紫陽花の見ごろぬかるむ三千院〉もまたしかり。「ぬかるむ」しか言っていないが、木立に囲まれた、あの三千院の道筋は、梅雨時でぬかるんで歩きにくかったに違いない。「言い惜しむことによって」得られた手柄でもある。 | ◎ | 夏葱をきざみ一分黙禱す |
| 岩井 充子 | |
| この句に言う「黙禱す」とは、八月十五日の終戦記念日を指すのであろう。あの日は確かに憎い戦争が終わった日でもあったが、この戦争で命を落とした三百十万人の日本人の忌とも思えるから「終戦忌」の季語も生まれた。総理大臣をトップとする慰霊祭が毎年行われ、その様子はNHKテレビで、正午前から放映されている。私も父をあの戦争で亡くしているので、この番組は毎年必ず見ている。 作者の岩井さんが、あの戦争とどうかかわり合うか知る由もないが、戦争の無残さを知る年代であることだけは確かだろう。私と同じようにNHKの正午の時報とともに聞こえる「黙禱」の声に合わせて目をつむり頭を下げた。その折の「夏葱をきざみ」の〝俗〟が、あの戦争を終えてから七十四年という時間の重さを改めて思わせるところだろう。 | ◎ | 風鈴や無為のいちにち心足り |
| 下山永見子 | |
| この一句の無為を仏教用語の有為に対して考えると堅くなるが、これといって、なすべき事がなかった一日くらいの意にとって読めば、季語の風鈴の音も心の奥に澄んでくる。私の日常もやはりそうで、処理しなくてはならない仕事を処理しないで終えた一日など、こんな感慨になる。 もっと言えば処理するという道理より、私にとって、処理しないことの非道理に出遭う喜びだとも思っている。これも齢を重ねてきたことにより得た幸いなのかも知れない。 | ◎ | 祭酒氏子顔して与れり |
| 露木 敬子 | |
| 露木さんの住む神奈川県の寒川町は相模一宮の寒川神社のある町だから、こんな祭りが残っているのだろう。ただし「氏子顔して与(あずか)れり」の主人公はまさか女性の作者ではなく、町の他の男性に違いない。氏子でもないから普段は寺社の行事の手伝いもしない人なのに、祭りの払いに振る舞われる酒の席には必ずいて、人一倍飲む。側にいる人の言葉を借りて言えば、まさに「氏子面(づら)して」ということになる。女性の目から見た目は優しすぎる。 | ◎ | コスモスや今年の藍の染め納め |
| 馬場 昭子 | |
| 馬場さんの住む福島県の三島町は、三十年前に訪れた奥会津の最初の町である。この町の別名を「てわっさの里」と呼ぶ。「てわっさ」とは手わざのことで、手工芸による品々が作られ、現在の上皇后が手にされた手編みの籠もこの町周辺で作られたという。馬場さんはそんな中の藍染めの作品を作っているのだろう。その藍も今年の染め納めともなると、辺りに漂っている藍甕からの藍の匂いとも別れとなる。コスモスが咲き、間もなく嗅くて嫌われる亀虫の群れが、家々の白壁に目立ち始める季節でもある。 | ◎ | 秋時雨山門の赤濃くなりし |
| 吉田 洋子 | |
| 寺院の本堂の前にある山門はほとんどが朱塗りだが、時代を経ているから、普段はくすんで見える。そんな折り秋時雨が降り、表面を曇らせていた汚れが取れて、本来の朱色が際立って見えたのだろう。普段見慣れている景の違いに気付くことも、俳句には大事なことだろう。 | ◎ | 棚経や三代前を聞かす僧 |
| 松岡 郁夫 | |
| 盂蘭盆会の折りに、僧が檀家の仏前にやって来て経を上げることを棚経と呼んでいる。その折り僧は作者の知らない三代前の曾祖父母の代の話をしてくれたのだろう。自分の知らない家系にもう一頁新しいものが加わった。この体験は子供のころの回想かも知れない。 | ◎ | 稜線の近くなりたる晩夏光 |
| 岡本りつ子 | |
| 岡本さんの住む奥会津は山に囲まれる地形だから、日常もこの山々に左右される。夏の暑い盛りの山々は、どこかぼやっと見えていたが、涼風の吹く頃ともなるとくっきり見え始める。そろそろ大根の種を蒔く時節かなと思ったのだろう。 | ◎ | 大根蒔く七十路はまだ男坂 |
| 渡部 華子 | |
| 前句でも触れた大根の種蒔きの時節は、八月の末ごろだが、このころは暑く雨もなかなか降らないから、農家にとっては大変な季節だ。暑さとこの労働を思うと、普通は気も滅入るが、この作者は、まだまだ男坂を上る体力も気力も残っていると、自らに言い聞かせているようだ。 | ◎ | 木犀のほどよき遠さありにけり |
| 佐藤 享子 | |
| もう五十年も前の話だが、私の買った古家の玄関脇に木犀の大木が一本植わっていた。悪いことに花の季節になると匂いが家中に籠もり、たまらなくなった私は、植木屋に頼んで伐ってしまった。ことほど左様に、木犀の匂いは、この一句のようにほどよい遠さがかなっている。 | |

